Nichiren・Ikeda
Search & Study
 32 厳護(32)
32 厳護(32)
「創価班」は、決然と立ち上がった。青年たちの若々しい力によって、学会の前進の歯車は、唸りをあげて回り始めたのである。
第一回総会での、会長・山本伸一の指導をもとに、「創価班」の首脳幹部たちは、真剣に語り合った。
――「創価班」を、山本先生の心を体した、学会精神あふれる、理想的な人材育成機関にするためには、どうすればよいか。
「山本先生は、『創価班』に、学会を守り抜くように指導されたが、『輸送班』の時代から、先生が、常に教えてくださったのは、『学会厳護』の精神だった。そして、その精神を体現できるようにするために、教育、訓練にも力を入れてくださった。これは、今後も、絶対に継承していかなければならないことではないかと思う」
「同感だ。訓練というと、何か古いことのように思われがちだが、一つ一つのことを、本当に身につけていくには、体で習得していく以外にない。したがって、これからも訓練が不可欠だ」
「そうだね。そして、各人が、『創価班』で受けた教育、訓練をもとに、日々の生活のなかで、それを、さらに自分のものとし、社会にあって、大いに力を発揮できるようにしていくべきだ。つまり、『創価班』で、『自己教育』『自己訓練』『自己啓発』の基盤を確立していくんだ」
御聖訓には「金は・やけば真金となる」と仰せである。人材も鍛錬を重ねなければ、大リーダーには育たない。鍛えこそ、大成の要件である。
「輸送班」の時代から、メンバーは、輸送の絶対安全を確保し、学会員を守り抜くために、時間厳守などを確認し合い、互いに厳しい訓練を課してきた。もし、着任の際に、万が一にも、輸送班員が遅れるようなことがあれば、大事故につながりかねないからだ。
また、休暇を取って、任務に就くには、職場の信頼を勝ち取らねばならない。したがって、職場でも、毎日が戦いであった。
 33 厳護(33)
33 厳護(33)
「輸送班」の任務を遂行するには、事前の万全な体調管理も不可欠である。
また、着任に際しては、頭髪もきちんと整え、シャツなども清潔感があふれる白にするように定められていた。輸送班もまた、学会の″顔″となるだけに、身だしなみも、きちんとすることが大事であるからだ。
列車の乗り換え時間や到着時刻、注意事項などを、登山会参加者に徹底することも、彼らの大切な任務であった。それには、担当した車両の隅々にまで、声が届かなければならない。そのために、発声練習に励むメンバーもいたのである。
連絡や報告の、迅速さ、正確さも、厳しく求められた。正確で、要を得た報告の仕方を、皆、必死になって習得した。もしも、登山会参加者の数が一人でも違っていれば、輸送上も問題が生じるし、宿泊の寝具や食事の数にも影響が出てきてしまうからである。
正確であることは、一切の基本である。不正確な情報こそ、諸問題の元凶となる。
イタリアの思想家マッツィーニは言った。
「全体の勝利は種々の行動が遂行されるその正確さによる」
さらに、総本山の建物の名前と位置をはじめ、地図は、すべて頭に入っていなければならない。参道に階段があれば、何段なのかも覚えておく必要があった。
もし、災害などで、暗闇の中を避難誘導する時にも、階段は何段かを告げれば、事故を未然に防げるからだ。
宿泊する各坊などの建物の構造と畳の数、収容人員、消火器や掃除用具のある場所、非常用の出入り口や通路、下足箱には靴が何足入るかなども、頭に叩き込んだ。
本当に、登山会参加者の安全の責任をもとうと思えば、あらゆる事態を想定し、万全の手を打たなければならない。
青年たちは、それに見事に対応していった。夏季講習会などには、海外からの登山会参加者も増加の一途をたどっていたことから、自主的に語学を勉強するメンバーもいた。
 34 厳護(34)
34 厳護(34)
「輸送班」の人材育成のなかで、最も驚嘆すべきは、何よりも、一人ひとりの、強い責任感を育んできたことである。
輸送班員は、任務に就く何日も前から、真剣に登山会の無事故と大成功を祈念し、唱題した。登山会の日が、好天に恵まれず、激しい雨などになると、皆、自分の問題としてとらえた。そして、次回は、断じて、晴天の登山会にしようと、さらに、真剣な祈りを捧げるのである。
天気は自然現象であり、不可抗力と考えるのが普通である。もし、荒れた天気になったとしても、「輸送班」の責任ではない。
しかし、彼らは、「教主釈尊をうごかし奉れば・ゆるがぬ草木やあるべき・さわがぬ水やあるべき」との御金言を、深く心に刻んでいた。
「教主釈尊」とは、ここでは大宇宙の一切の根源を指し、御本尊を意味している。その御本尊に真剣に祈りを捧げるならば、万物が動くのだとの仰せである。
また、御書には、「一身一念法界に遍し」とある。われらの一念は、大宇宙を遍く包むのである。
「輸送班」の青年たちは、仏法の法理に照らすならば、祈りの一念は、天候にも影響をもたらすとの確信のうえから、すべて自分たちの問題ととらえていたのである。そして、激しい雨になった場合には、″一人も、風邪など、ひかせるものか!″と、自らは、ずぶ濡れになりながらも、細心の注意を払って、任務の遂行にあたったのである。
まさに、それは、山本伸一の生き方にほかならなかった。彼は、会長就任以来、「自然災害がないように」「豊作であるように」、さらに「登山会が無事故で終わるように」と懸命に祈り続けてきたのである。この一念の結合が、師弟である。
伸一は、以前から、「輸送班」が自分と同じ心で、大宇宙をも動かしゆこうとの気迫で唱題し、会員を守ろうとしてくれていることに、深く、深く感謝してきた。
 35 厳護(35)
35 厳護(35)
古代ローマの詩人ホラティウスは、「訓練で隠された力が発揮されるのだ」と述べている。
頭で理解し、わかっていることと、実際にできることとは違う。災害の時なども、知識はあっても、いざとなると、体がすくんで動けなくなるケースが少なくない。訓練を繰り返し、習熟していってこそ、教えられたことが、実際に行えるようになるのだ。訓練とは、体で、生命で習得していくことである。
現代社会の問題点の一つは、人命などを守るために、青年たちが訓練を受ける機会が、ほとんどないことといえよう。
そうしたなかにあって、創価学会は、青年を鍛錬し、教育する、社会貢献の一大研修機関の役割を担ってきた。
「創価班」では、「輸送班」以来の実地訓練を大切にし、その精神を受け継ぐとともに、さらに、新時代のリーダーにふさわしい教育ができるように、検討を進めていった。
山本伸一は、「創価班」への激励には、生命を削る思いで力を注いだ。その後も総会に出席し、自ら研修も行った。メッセージや随筆、詩なども贈った。「創価班」を讃え、詠んだ歌や句は、数限りない。伸一は、彼らが体を張って、学会厳護の使命を果たしていることに、応えたかったのである。
寒風に
一人立ちたり
創価班
「学会を護る」「会員を大切に」「陰の戦いに徹する」を基本精神とする「創価班」は、まぎれもなく、伸一の精神を実践している弟子である。ゆえに、彼らこそ、後継の宝の人材であると、伸一は強く確信していたのだ。
ともあれ、伸一は、一九七七年(昭和五十二年)の本格的なスタートを、「創価班」と共に、青年と共に切った。それは、青年が全面に躍り出て、青年が戦う、炎のごとき青年学会をつくろうとする、彼の決意の表明であった。
 36 厳護(36)
36 厳護(36)
この一九七七年(昭和五十二年)「教学の年」は、例年にも増して、仏法研鑽の息吹に満ちあふれた年であった。
「教学の年」の開幕を前に、早くも前年十二月には、任用試験が行われていた。
そして、年が明けた一月九日には、全国各地で教学部の中級登用筆記試験が実施され、助教授、助教授補のメンバー四十五万人が受験したのである。
一月二十三日、中級登用筆記試験の合格者を対象に、面接試験が行われた。その日、大阪にいた山本伸一も、関西センターでの面接試験の試験官を務めた。また、試験の前後には、受験者らを激励した。
さらに、二月六日には、全国各地で一斉に初級登用試験が行われ、講師、助師のメンバー、四十三万三千人が受験している。
また、一月末から二月中旬にかけては、教授認定試験も行われた。その日時、方法は、方面、県によって異なり、筆記試験、面接試験、論文審査のいずれかの方法で、実施されることになっていた。この教授認定試験の審査委員会の委員長には、山本伸一自らが就いていたのである。
教授の多くは、自身も教授認定試験の勉強に励みながら、任用や中級、初級試験の学習会を担当したのだ。皆、多忙を極めたが、活気に満ちあふれ、はつらつとしていた。
試験の学習会を担当するなかで、受験するメンバーが、日々、仏法への確信を深め、歓喜に燃え、着実に成長を重ねていくのを、実感していたからだ。
教学を教えることは、信心を教えることであり、人材を育成することである。
そして、仏法の法理を、懸命に、懇切丁寧に語り説いていくなかで、自然に、自身の生命もまた歓喜し、躍動してくるのである。
大聖人は、「法華経を一字一句も唱え又人にも語り申さんものは教主釈尊の御使なり」と仰せである。ゆえに、共に御書を拝し、仏法を語る時、仏の大生命を涌現させることができるのである。
 37 厳護(37)
37 厳護(37)
一九七七年(昭和五十二年)の大教学運動の原動力となったのは、聖教新聞の元日付から四回にわたって掲載された、山本伸一の「諸法実相抄」講義であった。
伸一は、この講義の冒頭、鳩摩羅什の話を通し、創価学会がめざす教学運動について、語っていった。
鳩摩羅什は、亀茲国に生まれ、七歳で仏教を学び始め、不朽の名訳「妙法蓮華経」などを翻訳した訳経者である。彼が仏法の真髄を伝えようと、長安(現在の西安)で、仏典の翻訳作業に従事したのは、五十歳過ぎであった。
以来、逝去までの八年とも、十二年ともいわれる間、すさまじいまでの勢いで翻訳作業を重ねていく。それは、一カ月に二巻、乃至三巻という、驚異的なペースであった。
彼のもとには、名声を聞いて、俊英が、続々と集まって来ていた。その数は、時には八百人、時には二千人ともいわれた。羅什は、その聴衆を前に、教典を手にして、講義形式で翻訳を進めていったのである。
なぜ、そう訳すのか、その経文の元意はどこにあるのかを話し、時には、質疑応答のようなかたちを取りながら、納得のいくまで解読していった。
羅什の翻訳は、一人で書斎にこもり、辞書と首っ引きで、難解な用語を連ねていくような翻訳作業ではなかった。大衆の呼吸をじかに感じながら、対話の場で仏法を展開し、訳出していったのだ。そのなかから、彼の、極めて滑らかで、経文の元意をふまえた、優れた意訳が生まれたのである。
伸一は、そうした羅什の翻訳の様子を紹介し、力強く宣言したのである。
「人びとと語り、生活のなかでの実践を通し、思想の光は輝いていくものであります。
私どもの教学運動も、羅什と同じ方程式に則り、御書という教典を手にし、ある時は講義形式を取り、ある時は、質疑応答の形式を取り、ある時は、個人指導の際に、人びとの呼吸を、直接、実感しながら、対話の場で仏法を展開していくのであります」
 38 厳護(38)
38 厳護(38)
山本伸一は、釈尊が、いかにして法を説いていったかにも言及した。
「釈尊の八万法蔵という膨大な教説を、天台は、『五時八教』に判別しています。そう聞くと、精密に体系立てられた教理を思い浮かべ、釈尊も、そのカリキュラムに沿って説法したかのように受け取りがちであります。
しかし、釈尊の説法は、貧苦にあえぐ庶民への激励であり、病に苦しむ老婦人を背に負わんがばかりの同苦の言葉であり、精神の悩みの深淵に沈む青年への、温かな励ましの教えでありました。
差別に悩み、カースト制度に苦しむ大衆の側に立った、火のような言々句々が、その一生の教化を終えてみれば、八万法蔵として残ったということでありましょう。それは、経文が徹底して問答形式で説かれていることに、象徴的に表れています。
いわば、庶民との対話、行動のなかで、ほとばしり出た釈尊の悟りの法門が、経典としてまとめられていったのであります」
伸一は、日蓮大聖人の膨大な御書もまた、同様であると語った。
「御書は、大聖人が、激動の日々のなかで、民衆一人ひとりとの対話を続けられ、朝に夕に、救済の手を差し伸べられた結晶であります。戦いながら書き、語り、書き、語られながら、戦われたのであります。
仏教と聞けば、山野にこもり、静的なものと考えられがちでありますが、その発生から、既に実践のなかに生き、民衆のなかで生き生きと語り継がれてきたのが、その正統な流れであることに、私は刮目したいのであります」
仏法は、一切衆生を、なかんずく苦悩にあえぐ民衆を、救わんがための教えである。
ゆえに教学は、民衆の日々の生活に根差し、行動の規範となっていかねばならない。そして、人生の確信、信念となり、困難や試練を克服する力となってこそ、生きた教学といえるのである。それを現実に成し遂げてきたのが、創価の教学運動である。
 39 厳護(39)
39 厳護(39)
日蓮仏法の大哲理は、創価学会員という市井の人びとのなかに、確固たる哲学、思想として、生き生きと脈打っている。
「強い思想を代表しているかぎり、人間は強い」とは、精神分析の創始者フロイトの洞察である。
わが同志たちは、広宣流布の行く手を阻む障害が競い起これば、「此の法門を申すには必ず魔出来すべし魔競はずは正法と知るべからず」と自らを鼓舞し、いよいよ強盛な信心を奮い起こしてきた。
どんなに厳しい環境にあっても、「浄土と云うも地獄と云うも外には候はず・ただ我等がむねの間にあり」と、一喜一憂することなく、自身の境涯革命をめざして仏道修行に励んできた。
病に苦しむ時には、″「南無妙法蓮華経は師子吼の如し・いかなる病さはりをなすべきや」だ。仏の大生命力よ出でよ!″と、強盛に唱題を重ねた。
ある人は、「月月・日日につより給へ・すこしもたゆむ心あらば魔たよりをうべし」との御文のままに、日々、自分自身に挑戦し、学会活動に取り組んでいる。そして、「一丈の堀を越えざる者二丈三丈の堀を越えてんや」と、一つ一つの目標に向かい、着実に、粘り強く、前進の歩を進める。
また、ある人は、「御みやづかいを法華経とをぼしめせ」と、懸命に仕事に挑戦し、職場で勝利の実証を示そうと努力している。
さらに、「教主釈尊の出世の本懐は人の振舞にて候けるぞ」との一節を座右の銘とし、人格を磨き、仏法の人間主義の体現者たらんと奮闘する同志もいる。
創価学会の教学運動によって、法華経が、日蓮大聖人の仏法が、生活法として、民衆の哲学として、現代に蘇ったといってよい。
山本伸一は、この教学運動の潮流を、さらに広げ、本格的な民衆仏法の時代を開き、「生命の世紀」を建設しようと心に誓っていた。
 40 厳護(40)
40 厳護(40)
この一九七七年(昭和五十二年)を、創価学会が「教学の年」と定めたのは、山本伸一の提案によるものであった。広宣流布の新章節を迎えた学会が、さらに大飛躍を期すためには、これまで以上に、全同志が、御書を心肝に染めなければならないと考えたからだ。
人間とは何か。生命とは何か。自己自身とはいかなる存在なのか。なんのための人生なのか。幸福とは何か。生とは何か。死とは何か――仏法は、そのすべての、根本的な解答を示した生命の哲理である。
したがって、仏法を学び、教学の研鑽を重ねることは、人生の意味を掘り下げ、豊饒なる精神の宝庫の扉を開く作業といってよい。
日蓮大聖人は、「行学の二道をはげみ候べし、行学たへなば仏法はあるべからず」と仰せである。
信仰の実践とともに、教学を学んでいかなければ、仏法の本義を深く理解し、信心を究めていくことはできないからだ。
第二代会長・戸田城聖も、こう訴えている。
「信は理を求め、求めたる理は信を深からしむ」「教学により信心が強くなり、高まるから、功徳がでる」と。
大聖人は、「心の師とはなるとも心を師とせざれ」との経文を引かれて、仏法者の在り方を指導されている。その「心の師」となるべき、仏法の法理を学ぶのが教学である。
教学は、自分の生き方、振る舞いが、仏法者として、正しいのかどうかを見極める尺度であり、自己を映し出す明鏡となるのだ。
また、教学は、仏道修行を妨げる三障四魔や諸難に翻弄されることなく、一生成仏、広宣流布へと至る航路を照らす″灯台″となる。
さらに、一切衆生に仏の生命が具わっていることや、三世にわたる生命の因果の理法を学ぶことは、人間の根本的なモラル、道徳の規範を確立していくことでもある。
創価学会の人間革命運動を推進していくには、教学が不可欠であるというのが、伸一の思索に思索を重ねた結論であったのである。
 41 厳護(41)
41 厳護(41)
戦後の創価学会再建にあたって、戸田城聖が、全精魂を注いできたのは、教学を一人ひとりの生命に打ち込むことであった。
戸田は、戦時中、軍部政府の弾圧で逮捕された二十一人の幹部のうち、会長の牧口常三郎と自分以外は、皆、退転するという一大痛恨事を体験した。
主が投獄された一家は、生活の柱を失い、食べていくこともできない事態に直面した。そのうえ、「非国民の家」と罵られ、悲嘆に暮れた家族が、まず、信心に疑いをもち、退転し始めた。妻は夫に、「信心をやめて、一日も早く帰ってくるように」と、涙ながらに懇願するのである。そして、幹部たちは、次々と軍部権力に屈していったのだ。
また、投獄されぬ者も、弾圧を恐れて、大多数が、愚かにも信仰を捨てたのである。
出獄後、戸田は、悔し涙に暮れた。
″もし、皆が、「行解既に勤めぬれば三障四魔紛然として競い起る」との文を心肝に染めていたならば、仏法の法理への不動の確信に立ったであろう″
一方、牧口は、獄中から家族に宛てた手紙に、「三障四魔ガ紛起スルノハ当然デ、経文通リデス」と、歓喜をもって記している。
牧口の御書には、「開目抄」の「詮ずるところは天もすて給え諸難にもあえ身命を期とせん」に赤線が引かれていた。彼は、大難に遭い、御書を身で読むことができた喜びのなか、殉教していったのである。
また、戸田は「在在諸仏土 常与師倶生(在在の諸仏の土に 常に師と倶に生ず)」(法華経317㌻)の一節を胸に、牧口の不二の弟子として、獄中闘争を貫き通した。
″同志の退転は、信心への確信なく、教学に暗いゆえである。二度と同じ轍を踏むまい″
こう痛感した戸田は、学会の再建に、教学をもって臨もうと、終戦の翌年にあたる一九四六年(昭和二十一年)の元日から、法華経講義を開始した。さらに、「観心本尊抄」「開目抄」「立正安国論」など、御書の講義を中心に、人材の育成にあたったのである。
 42 厳護(42)
42 厳護(42)
山本伸一は、「教学の年」を迎えるにあたって、新時代建設の教学運動を推進するには、どの御書から研鑽すべきか、熟慮を重ねた。そして、「諸法実相抄」講義をもって、スタートを切ることにしたのである。
日蓮大聖人が、本抄の「追申」で、「ことに此の文には大事の事どもしるしてまいらせ候ぞ」と仰せのように、この御書には、仏法の肝要が集約して表されているからだ。
本抄は、文永十年(一二七三年)五月、五十二歳の御述作で、佐渡流罪中に、一谷から最蓮房日浄に与えられた御手紙である。
法華経迹門の、在世衆生得脱のカギとされた「諸法実相、十如是」の文から説き起こして、法華経の哲理の真髄を示し、その当体が妙法蓮華経、即、御本尊であることを教えられている。つまり、法本尊の意義が明かされているのである。
さらに、この法華経を弘むべき人こそ、地涌の菩薩の上首上行であることを示され、それを、まさに大聖人御自身が実践してきたと述べられている。すなわち、大聖人こそ、一往、外用の辺から言えば、上行菩薩の再誕であり、再往、内証の辺から言えば、末法救済の大法を建立する御本仏であり、久遠元初の仏であることを暗示されている。
いわば、この一書のなかに、人本尊開顕の書「開目抄」と、法本尊開顕の書「観心本尊抄」の結論が包含されているのである。
しかも、後半では、未来の広宣流布は間違いないことを予言され、末法万年にわたる仏道修行の要諦として、信行学の在り方を教示されて結ばれている。まさに、本抄には、日蓮仏法の本義が明確に示されているのだ。
ゆえに伸一は、この御書に照らして、「本当の信心とは何か」「大聖人の弟子の実践とは何か」、そして「創価学会出現の意義と使命」とを明らかにしたいと考えたのである。
御書という明鏡こそが、われらの一切の規範であり、指針である。御書に帰ることが大聖人直結であり、そこに信心の王道がある。
 43 厳護(43)
43 厳護(43)
「諸法実相抄」講義で山本伸一は、大宇宙、社会の一切の現象は、妙法の姿であること、そして、御本尊は、大宇宙の縮図であり、根源であることを述べていった。
また、仏は、架空の抽象的存在ではなく、釈尊も、多宝仏も、妙法の力用の具体的表現であることを論じた。
次いで、「凡夫こそ本仏」「一切の衆生が妙法の当体」とする日蓮大聖人の法理は、過去の仏法観を根底から打破するものであり、ここに、人間主義の偉大なる原理があることを強調した。
さらに、伸一は、法華経では、仏の久遠の弟子にのみ、妙法弘通の使命を託しており、末法今時に妙法を弘めている人、すなわち、折伏している人は、仏の久遠の弟子であり、地涌の菩薩であることを訴えた。
まさに、この末法広宣流布の果敢な闘争のなかにこそ、大聖人門下の真実の信仰があるのだ。そして、これこそが、法華経に説かれた、「如来の使にして、如来に遣わされて、如来の事を行ず」(法華経357㌻)なのである。
ここで彼は、地涌の菩薩について言及していった。
「地涌の菩薩とは、人から言われて動くものではない。宇宙本然の妙法に生き切るがゆえに、大地から草木が本然的に生長していくように、自ら題目をあげ、社会のために、平和のために、貢献していく生命であります」
戸田城聖は、戦時中の獄中闘争のなかで、「われ地涌の菩薩なり」との悟達を得た。
そして、自ら、「折伏の師匠」であり、創価学会は「世界でただ一つ、末法の正法正義を弘めゆく折伏の団体である」と宣言した。学会本部常住の御本尊には、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」とお認めである。
戸田は、常々、語っていた。
「御本仏・日蓮大聖人より、末法現代の広宣流布を託された地涌の菩薩の集いであり、仏意仏勅の団体こそ、創価学会なのだ」
これが、戸田の大確信であった。
 44 厳護(44)
44 厳護(44)
一月の五日付には、山本伸一の「諸法実相抄」講義の第三回が掲載された。
この回からは、弟子の信仰の在り方や、広宣流布への実践方法が説かれていく。
「いかにも今度・信心をいたして法華経の行者にてとをり、日蓮が一門となりとをし給うべし……」に入ると、講義には、一段と力がこもっていった。
伸一は、この「いかにも」、つまり″なんとしても″という言葉のなかに、″今こそ、弟子たちを成仏させずにはおくものか!″という、大聖人の大情熱と大慈大悲を、強く、深く、拝するのである。
日蓮大聖人の弟子たちは、自らが地涌の菩薩であることを知らず、過去遠遠劫にわたって、無明の闇夜をさまよい、生死流転を繰り返してきた。しかし、今世において、大聖人の門下となり、大仏法と巡り合ったのだ。
しかも、師匠である大聖人は、竜の口の法難を経て、地涌の菩薩の上首・上行菩薩にして、末法の御本仏であることを、いよいよ示されたのである。
さらに、法難の嵐は、弟子たちにも吹き荒れていた。法華経の経文を身で読める好機である。末法広宣流布に立つ時が来たのだ。一生成仏の千載一遇の機会が到来したのだ。
″弟子たちよ、何ものも恐れるな! この時を断じて逃すな! 今こそ、勇気をもって立ち上がるのだ。真の信心に立ち、法華経の行者となって、生涯、日蓮の一門となり通していくのだ!″
その烈々たる大聖人の叫びが、伸一の胸に、雷鳴のように響くのである。
伸一は、訴えた。
「『日蓮が一門』の自覚に立つということは、具体的な私どもの実践に約して申し上げれば、学会と運命を共にし、広宣流布への異体同心の世界に生き切ることであります。
なぜかならば、創価学会は、ことごとく御書に仰せの通りに実践し、三類の強敵と戦っている、御本仏・日蓮大聖人の生命に直結した唯一の広布実践の団体であるからです」
 45 厳護(45)
45 厳護(45)
山本伸一の講義は、「日蓮と同意ならば地涌の菩薩たらんか、地涌の菩薩にさだまりなば釈尊久遠の弟子たる事あに疑はんや」に入った。
「『日蓮と同意』とは、大聖人と同じ心、同じ精神ということであります。
大聖人は、『日蓮生れし時より・いまに一日片時も・こころやすき事はなし、此の法華経の題目を弘めんと思うばかりなり』と仰せです。
この心で、広宣流布の使命に生き、生命をかけて実践し、責任をもっていく人が、大聖人の真の弟子であり、地涌の菩薩です。口先や、形式だけの行動であれば、やがて、大聖人のお叱りを受けることでしょう。
初代会長の牧口常三郎先生は、死身弘法の殉教の生涯であられた。第二代会長の戸田城聖先生も、まさに、『日蓮と同意』の、不惜身命の戦いを貫かれた。お二人の信力、行力の福徳によって、御本尊の仏力、法力という功力は、創価学会の信心のうえに、燦然と輝き渡っているのであります。
また、大聖人は、地涌の菩薩であるならば、『釈尊久遠の弟子』であることも、疑う余地がないと明言されているのであります」
釈尊とは、一往は、法華経本門の教主・釈尊だが、再往は、久遠元初の自受用報身如来であり、末法の御本仏・日蓮大聖人である。
伸一は、毅然と訴えた。
「私たちは、地涌の菩薩であり、大聖人の本眷属たる久遠の弟子なるがゆえに、末法広宣流布の大舞台に躍り出たのであります。
使命深き、大聖人直結の私たちです。本当に、広宣流布の大責任に立って悩み、苦しみ、祈り、戦うならば、大聖人の、南無妙法蓮華経の御命が湧いてこないわけがない。
私自身、誰も頼ることもできず、ただ一人で、決断し、敢然と進まねばならない時も、断固、その確信を貫いてまいりました」
伸一の心には、常に″大聖人直結の信心を貫いてきたのは、われら創価学会である″との、富士のごとき不動の大確信があった。
 46 厳護(46)
46 厳護(46)
山本伸一は、地涌の菩薩の本領とは何かについて、掘り下げていった。
「菩薩の本領は、『誓願』ということにあります。そして、地涌の菩薩の誓願とは、『法華弘通』にあります。ゆえに、心から周囲の人びとを幸せにしきっていく、広宣流布への『誓願』の唱題が大切です。厳しく言えば、『誓願』なき唱題は、地涌の菩薩の唱題ではないのであります」
「誓願」には、魔に打ち勝ちゆく、仏の生命のほとばしりがある。
伸一は、全同志が、一人も漏れなく、大功徳に浴してほしかった。病苦、経済苦など、すべてを乗り越えて、幸せになってほしかった。そのための祈りの要諦こそ、「広宣流布への誓願」なのである。
皆、それぞれに、さまざまな問題や苦悩をかかえていよう。その解決のためには、″広宣流布のため″との一念が大事になるのだ。
たとえば、病に苦しんでいるならば、″この病を克服し、仏法の正しさを必ず証明します。広宣流布に、自在に動き回るために、どうか大生命力をください″との誓願の心が、克服の大きな力となるのだ。
題目を唱えれば、もちろん功徳はある。しかし、″病気を治したい″という祈りが、深き使命感と一致していく時、自身の根本的な生命の変革、境涯革命、宿命の転換への力強い回転が始まる。
広宣流布を誓願し、唱題に励む時、自身の胸中に、地涌の菩薩の大生命が涌現し、日蓮大聖人の御命が脈動して、己心の仏界が開かれるのである。そこに、境涯革命があり、宿命の劇的な転換も可能になるのだ。
また、弘教など、広宣流布のための挑戦課題を成就せんと悩み、唱題すること自体、既に地涌の菩薩の生命である。ゆえに、その実践のなかで、個々人のさまざまな苦悩も、乗り越え、解決していくことができるのだ。
地涌の大生命という赫々たる太陽が昇れば、苦悩の闇は消え去り、幸福への確たる道を、雄々しく歩み抜いていくことができる。
 47 厳護(47)
47 厳護(47)
山本伸一は、「日蓮一人はじめは南無妙法蓮華経と唱へしが、二人・三人・百人と次第に唱へつたふるなり……」の御文では、「一人立つ」勇気の信心を力説した。
「いつの時代にあっても、絶対に変わらない広宣流布の根本原理が、『一人立つ』ということです。大聖人も、そして牧口先生も、戸田先生も、決然と一人立たれた。これが、仏法の精神であり、創価の師子の心です。
『一人立つ』とは、具体的に言えば、自分の家庭や地域など、自身が関わっている一切の世界で、妙法の広宣流布の全責任をもっていくことです。
私たちは、一人ひとりが、家族、親戚、友人等々、他の誰とも代わることのできない自分だけの人間関係をもっています。妙法のうえから見れば、そこが使命の本国土であり、その人たちこそが、自身の眷属となります。
自分のいる、その世界を広宣流布していく資格と責任を有しているのは、自分だけです。
ゆえに、『一人立つ』という原理が大事になります。御本仏・日蓮大聖人の御使いとして、自分は今、ここにいるのだと自覚することです。そして、おのおのの世界にあって、立ち上がっていくのが、地涌の菩薩です。そのなかにのみ、広宣流布があることを忘れないでください」
最も身近なところで、仏法を弘めていくというのは、地味で、それでいて最も厳しい戦いといえる。自分のすべてを見られているだけに、見栄も、はったりも、通用しない。誠実に、真面目に、粘り強く、大情熱をもって行動し、実証を示しながら、精進を重ねていく以外にない。しかし、そこにこそ、真の仏道修行があるのだ。
「また、この御文は、広宣流布は、必ず、民衆の大地から盛り上がって、成就していくことを述べられたものです。それは、決して権力によって成されるものではない。仏法対話を通しての、民衆と民衆の魂の触発こそが、その原動力となるのであります」
 48 厳護(48)
48 厳護(48)
「諸法実相抄」講義で、山本伸一は、「流人なれども喜悦はかりなし」の御文を通し、絶対的幸福境涯について言及していった。
「日蓮大聖人は、流人という、まことに厳しく、辛い立場にあります。しかも、命を狙われ、いつ殺されるかもしれない状況です。普通に考えれば、悲嘆、絶望の世界です。多くの人は不幸と見るでしょう。
でも、そうとらえるのは、相対的次元での幸福観によるものです。
大聖人の内心に確立された御境涯では、この世で誰よりも豊かで、湧きいずる大歓喜の、広大かつ不動の幸福を満喫されているのであります。これが、絶対的幸福境涯です。
一般的に、幸福の条件というと、経済的に豊かであり、健康で、周りの人からも大事にされることなどが、挙げられると思います。
こうした条件を、満たしているように見える人は、世間にも数多くいるでしょう。しかし、本当に、それで幸せを満喫しているかというと、必ずしも、そうとは言えません。心に不安をかかえている人も少なくない。
これらは、相対的幸福であり、決して永続的なものではないからです」
どんなに資産家であれ、社会の激変によって、一夜で貧乏のどん底に陥る場合もある。健康を誇っていた人も、不慮の事故や病に苦しむこともある。さらに、加齢とともに、誰しも、さまざまな病気が出てくるものだ。
相対的幸福は、自己と環境的条件との関係によって成り立つ。したがって、環境の変化によって、その幸福も、はかなく崩れる。
また、欲するものを手に入れたとしても、自己の際限なき欲望を制御することができない限り、幸福の実感は、一瞬にすぎない。財などへの過度の執着は、むしろ、心を貧しくさえする。
「もし財産が人を傲慢や怠惰や無為や欲望や吝嗇にひき入れる場合には、不幸そのものとさえなる」とは、スイスの哲学者ヒルティの警句である。
 49 厳護(49)
49 厳護(49)
人は、財や地位、健康、名誉など、相対的幸福を願い、求めて、努力するなかで、向上、成長していくことも事実である。また、所願満足の仏法を持つ私たちは、強盛な信心によって、その願いを成就することができるし、それは、信仰の力の実証ともなろう。
しかし、崩れざる真実の幸福は、相対的幸福にではなく、絶対的幸福にこそあるのだ。
山本伸一は、大確信をもって訴えた。
「絶対的幸福とは、相対的幸福の延長線上にあるものではありません。相対的幸福の次元では、いくら不幸のように見えても、絶対的幸福を確立することができる。その例が、日蓮大聖人の『喜悦はかりなし』と仰せの御境涯です。
絶対的幸福とは、有為転変する周りの条件に支配されるのではなく、自分が心に決めた使命、目的に向かって実践していくなかで生ずる、生命自体の充実感、満足感です。
ここで最も重要なことは、自分が定めた使命、目的が、宇宙を貫く常住不変の法に合致していることです。結論すれば、広宣流布の使命を自覚し、大願に生き抜く心にこそ、真実の絶対的幸福が築かれるのであります」
広宣流布に生き抜く時、わが生命に、地涌の菩薩の、そして、仏の大生命が脈動する。流罪の身であろうが、獄中であろうが、あるいは、闘病の身であっても、そんなことには、決して煩わされることのない、大歓喜、大充実、大満足の生命が開かれていくのである。それが絶対的幸福である。
懸命に信心に励むなかで、その一端を体験している同志は、少なくないはずである。いかに貧しく、病苦をかかえながらも、地涌の使命に燃え、毅然と折伏に歩いた時の、あの生命の躍動と歓喜と充実である。
どんな豪邸に住んでいようと、仏法を知ろうともせず、学会を蔑み、水や塩を撒く人を見ると、心の底から哀れに感じ、″必ず、この人に、真実の幸せの道を教えてあげたい″と痛切に思ったにちがいない。その境地こそが、絶対的幸福境涯へと至る大道なのだ。
 50 厳護(50)
50 厳護(50)
戸田城聖は、支部総会などで、大病や経済苦を克服した体験発表を聞くと、同志の功徳を祝福しながらも、よく、こう語った。
「私の受けた功徳を、この講堂いっぱいとすれば、みんなの功徳は、ほんの指一本にすぎません。まだまだ小さなものです」
戸田は、頑健な体や、技能、大資産をもっていたわけではない。彼は、本当の大功徳とは、相対的幸福ではなく、絶対的幸福境涯の確立にあることを教えたかったのである。
山本伸一は、「諸法実相抄」講義で、祈るような思いで訴えた。
「広宣流布のために、祈り、法を弘める、私どもの日々の活動こそが、一生成仏への道であり、三世にわたる絶対的幸福を確立する直道なのであります。
どうか皆さんは、それこそが、人間として、最も尊い生き方であることを強く確信するとともに、最大の誇りとしていっていただきたいのであります」
伸一の講義の反響は、大きかった。
――「目の覚める思いで、講義が掲載された聖教新聞を読みました。仏法の精髄に触れた思いがします」「創価学会員として信心に励むことのできる喜びを、しみじみと、かみしめました」などの声が続々と寄せられた。
この「教学の年」(一九七七年)の伸一の講義は、「諸法実相抄」だけではなかった。教学理論誌の『大白蓮華』にも、一月号から「百六箇抄」講義の連載を開始した。
さらに、この年は、六回にわたる「生死一大事血脈抄」講義のほか、「報恩抄」「法門申さるべき様の事」「撰時抄」「開目抄」などの講義が、相次ぎ聖教新聞紙上に掲載されていったのである。
伸一は、日々、寸暇を惜しんで懸命に御書を拝し、思索に思索を重ねた。また、さまざまな会合で、御書を通して激励を重ねた。
自分は、ただ号令をかけるだけで、行動を起こさなければ、何事も進むことはない。
伸一は、自らの実践をもって、教学運動の新しい大波を起こそうとしていたのだ。
 51 厳護(51)
51 厳護(51)
一月十五日、大阪府豊中市の関西戸田記念講堂には、全国から四千五百人の教授代表が集い、晴れやかに教学部大会が開催された。
十二日の夜から、日本列島は寒波に見舞われ、積雪、レールのひび割れ、停電騒ぎ等が相次ぎ、列車などのダイヤは大幅に乱れた。
しかし、この日の朝、大阪地方は、まばゆい陽光に包まれたのである。
参加者は、「教学の年」の重要な行事となる教学部大会とあって、輸送機関の混乱をものともせずに、喜々として集って来た。
山本伸一は、この大会を、「教学新時代」の幕開けにしようと決意し、自ら記念講演も行おうと、準備に力を注いできた。
「教学新時代」とは、仏法の法理を現代社会に、世界に展開し、未来創造の新思潮を形成していく時代である。伸一は、それには、教学上の一つ一つの事柄を、″人間のための宗教″という視座に立って、根源からとらえ直し、その意味を明らかにするところから、始めなければならないと考えていたのだ。
教学部大会の式次第は進んだ。
一月半ばという真冬にもかかわらず、場内には、新しい思想運動を起こそうとする、参加者の熱気が満ちあふれていた。
最後に、伸一の登壇となった。皆、胸を躍らせながら、彼の話を待った。
伸一は、参加者の労をねぎらったあと、一気に本題に入った。
「仏教は、本来、革命の宗教なのであります。釈尊が仏教を興したのも、権威主義に堕し、悩める民衆の救済を忘れたバラモン教に対して、宗教を人間の手に取り戻すためであったことは、周知の事実であります。
″宗教のための人間″から″人間のための宗教″への大転回点が、実に仏教の発祥でありました。仏教は、まさしく、民衆蘇生のための革命のなかから生まれたと言っても、過言ではないのであります」
明快な語り口であった。誰もが″そうだ!″と思った。宗教が、儀式や権威のベールに包まれる時、その精神は衰退し、滅していく。
 52 厳護(52)
52 厳護(52)
仏教は、民衆の蘇生をめざして出発したにもかかわらず、やがて、戒律主義に偏して、出家僧侶を中心とする一部のエリートの独占物となっていく。
そんな仏教教団の在り方に対して、改革の烽火が上がり、釈尊滅後百年ごろ、仏教教団は分裂を招くことになる。従来の出家中心の保守的な「上座部」と、在家民衆に光を当てようとする、進歩的な「大衆部」に分かれていくのである。
そして、仏教を、釈尊の精神という原点から問い直そうという、本格的な宗教革命の流れが起こる。大乗仏教運動である。自利的で、形式主義に陥り、民衆の苦悩から遊離した出家仏教に対して、民衆救済の仏教への流れがつくられていったのである。
この仏教覚醒の大波が、インドから中国、さらに、日本へと広がっていくのである。
山本伸一は、強く訴えた。
「民衆のなかから生まれ、みずみずしく躍動した仏教が、沈滞、形骸化していった大きな要因のなかに、仏教界全体が″出家仏教″に陥り、民衆をリードする機能を失ったという事実があります。もともと仏教とは、民衆のものであり、出家たる法師もまた、民衆の指導者の意味であったのであります」
伸一は、釈尊の仏法が変質し、衰退していった要因を明らかにすることによって、日蓮仏法が、決して同じ轍を踏むことがないよう、戒めとしたかったのである。
その仏法興廃のカギを握ってきたのが、衆生を導く「法師」の存在である。ここで彼は、日寛上人の「撰時抄愚記」を引き、「法師」について論じていった。
「『大法師』とは、今はいかなる時かを凝視しつつ、広宣流布の運動をリードし、能く法を説きつつ、広く民衆の大海に自行化他の実践の波を起こしゆく存在なのであります。
そのためには、時代の激流を鋭く見極め、時には、民衆の盾となり、民衆と共に、仏法のために戦いゆくことが、法師の必要条件となるのであります」
 53 厳護(53)
53 厳護(53)
山本伸一は、自ら「法師」の尊い姿を示された方こそ、御本仏・日蓮大聖人であることを述べた。そして、「法師」の在り方を示された、大聖人の御指導を拝した。
「受けがたき人身を得て適ま出家せる者も・仏法を学し謗法の者を責めずして徒らに遊戯雑談のみして明し暮さん者は法師の皮を著たる畜生なり」
僧となりながら、勇気の実践なく、怠惰に流されていった者は、法師の皮を着た畜生であり、仏法の体内から、仏法を滅ぼしていくことへの、警鐘を鳴らされているのだ。
「末法の法華経の行者は人に悪まるる程に持つを実の大乗の僧とす、又経を弘めて人を利益する法師なり」
末法で法華経を行ずる大乗の僧は、人に憎まれ、大難を受け、果敢に戦いを続ける人なのだ。また、弘教に挺身し、民衆の救済に生き抜いていかねばならないと仰せなのだ。
それに対して、在家の在り方については、次のように述べられている。
「然るに在家の御身は但余念なく南無妙法蓮華経と御唱えありて僧をも供養し給うが肝心にて候なり、それも経文の如くならば随力演説も有るべきか」
僧侶は、専ら折伏に徹し、三類の強敵と戦い、広宣流布せよと言われているのに対して、在家は、ひたすら題目を唱え、供養し、力にしたがって仏法を語るべきであると言われているのだ。いわば、在家には、側面からの応援を託されているのである。
これらの御文を紹介したあと、伸一は、力を込めて語った。
「この在家と出家の本義に照らしてみるならば、現代において創価学会は、在家、出家の両方に通ずる役割を果たしているといえましょう。これほど、偉大なる仏意にかなった和合僧は、世界にないのであります」
現代において、誰が広宣流布を推進してきたのか。誰が法難を受けてきたのか――創価学会である。ゆえに、学会は、その精神、実践においては、出家、法師といえよう。
 54 厳護(54)
54 厳護(54)
山本伸一は、さらに「出家」の真意について掘り下げていった。
もともと「出家」とは、「家を出る」と書き、名聞名利の家を出て、煩悩の汚泥を離れる、との意味である。剃髪は、仏道を究めるまで、二度と家に帰るまいとの決意のしるしであった。
大乗経典の大荘厳法門経には、出家について、次のようにある。
「菩薩の出家は自身の剃髪を以て名けて出家と為すに非ず。何を以ての故に。若し能く大精進を発し、為めに一切衆生の煩悩を除く、是を菩薩の出家と名く。自身染衣を被著するを以て名けて出家と為すに非ず。勤めて衆生の三毒の染心を断ず。是を出家と名く」
菩薩とは、一切衆生の救済のために修行する人をいう。その菩薩の出家とは、ただ自分が髪を剃ることを出家というのではない。では、何をもってそう呼ぶのか。大精進を起こして、一切衆生の煩悩を取り除く――これを菩薩の出家というのである。
僧侶の衣を着ることを出家というのではない。力を尽くして、貪(むさぼり)、瞋(いかり)、癡(おろか)の三毒に、衆生の心が染まっていくことを断じていく――これを出家というのだ、との意味である。
形式ではない。どこまでも、民衆の真っただ中に飛び込み、人びとの苦悩をわが苦悩として戦うなかにこそ、真実の出家の道があるのだ。人びとを救うために何をするのか、何をしてきたのかこそ、問われねばならない。
伸一は、こうした考察を述べたあと、参加者に力強く呼びかけた。
「私ども学会員は、形は在俗であっても、その精神においては、出世間の使命感をもって、誇りも高く、仏法流布のために、いよいよ挺身してまいりたいと思うのであります」
盛んな賛同の拍手が鳴り響いた。
仏教の原点に立ち返るならば、権威や形式の虚飾が剥ぎ取られ、一切の本義が明快に照らし出されていく。参加者は、赫々たる太陽の光を浴びる思いで、伸一の話を聴いていた。
 55 厳護(55)
55 厳護(55)
山本伸一は、次いで、寺院の起源から、その意義について論じていった。
――釈尊の化導方式は、「遊行」であり、全インドを歩きに歩き、民衆のなかで仏法を説いた。
ところが、インドには雨期がある。一年のうち、三カ月間は遊行できない。その間、弟子たちは、一カ所に集まって修行に励んだ。その場所が、舎衛城の祇園精舎や、王舎城の竹林精舎など、「精舎」である。そこは、文字通り、修行に精錬する者のいる舎であり、これが、寺院の原形となるのである。
修行し、研鑽を深めた僧たちは、雨期が過ぎれば、また、各地に散っていった。つまり、当時の精舎は、現在の寺院のように、僧職者が、そこに住み、宗教的儀式を執り行うためのものではなかった。いわば、修行のための「拠点」であったのである。
後にインド仏教の中心となったナーランダー寺院では、研鑽も充実し、一種の大学の機能を果たしていた。各地から修行者が集まり、起居をともにしながら、仏教の教義、布教の在り方などを学び、一定の期間を終えると、各地に戻っていったのである。まさに、現代の学会の講習会、研修会を彷彿とさせよう。
寺院を意味する「伽藍」は、僧伽藍摩(サンガーラーマ)の略で、仏道修行に励む人びとが集まる場所であったことに由来している。また、寺院は、そこに集って仏道修行にいそしみ、成道をめざす場であったことから、「道場」ともいうのである。
伸一は、寺院本来の意義を明らかにし、大確信を込めて訴えた。
「創価学会の本部・会館、また研修所は、広宣流布を推進する仏道実践者が、その弘教、精進の中心拠点として集い寄り、大聖人の仏法を探究するところであります。そして、そこから活力を得て、各地域社会に躍り出て、社会と民衆を蘇生させていく道場であります。すなわち、寺院の本義からするならば、学会の会館、研修所もまた、『現代における寺院』というべきであります」
 56 厳護(56)
56 厳護(56)
最後に山本伸一は、法華経神力品の「日月の光明の 能く諸の幽冥を除くが如く 斯の人は世間に行じて 能く衆生の闇を滅し」(法華経575㌻)の、「世間に行じて」について述べていった。
「世間とは、社会であり、社会の泥沼のなかで戦うのでなければ、衆生の苦悩の闇を晴らすことは、不可能なのであります。
日蓮大聖人が、当時、日本の政治などの中心地であった鎌倉で、弘教活動を展開されたのも、『世間に行じて』との、経文通りの御振る舞いであります。ゆえに、世間へ、社会のなかへ、仏法を展開していかなければ、大聖人の実践、そして、目的観とは、逆になってしまうことを恐れるのであります。
今、私は、恩師・戸田先生が、昭和二十八年(一九五三年)の年頭、わが同志に、『身には功徳の雨を被り、手には折伏の利剣を握って、師子王の勇みをなしていることと固く信ずる』と述べられたことを思い出します。
私どもも、燦々たる元初の功徳の陽光を浴びながら、慈悲の利剣を固く手にし、師子王のごとく、この一年もまた、悠然と、創価桜の道を切り開いてまいりたいと思います」
共感と誓いの大拍手が轟いた。
伸一は、社会を離れて仏法はないことを、伝え抜いておきたかったのだ。
荒れ狂う現実社会のなかで、非難、中傷の嵐にさらされ、もがき、格闘しながら、粘り強く対話を重ね、実証を示し、正法を弘めていく。そこに、末法の仏道修行があり、真の菩薩道があるのだ。
原点を見失い、草創の心と実践を忘れた宗教は、形式化、形骸化し、儀式主義に陥り、官僚化、権威化する。そして、民衆を睥睨し、宗教のための宗教となる。それは、宗教の堕落であり、精神の死である。
日蓮仏法を、断じてそうさせてはならない。大聖人の大精神に還れ――仏法厳護のために伸一は、自ら大教学運動の旗を掲げ、決然と、新時代開拓の扉を開こうとしていたのである。
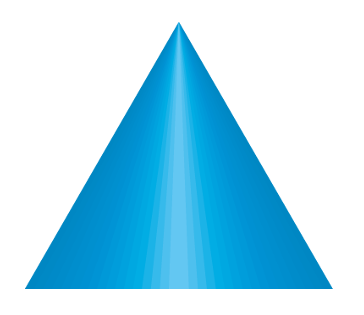
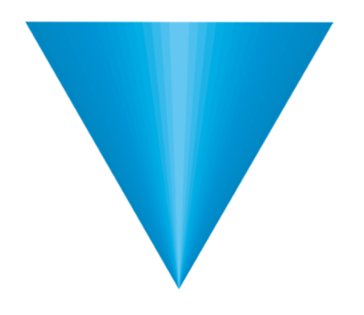
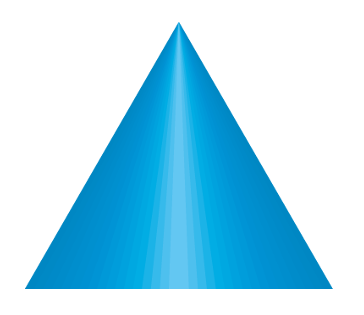
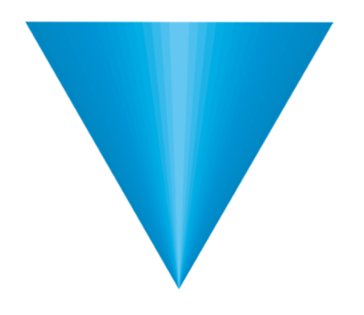
 32 厳護(32)
32 厳護(32) 33 厳護(33)
33 厳護(33) 34 厳護(34)
34 厳護(34) 35 厳護(35)
35 厳護(35) 36 厳護(36)
36 厳護(36) 37 厳護(37)
37 厳護(37) 38 厳護(38)
38 厳護(38) 39 厳護(39)
39 厳護(39) 40 厳護(40)
40 厳護(40) 41 厳護(41)
41 厳護(41) 42 厳護(42)
42 厳護(42) 43 厳護(43)
43 厳護(43) 44 厳護(44)
44 厳護(44) 45 厳護(45)
45 厳護(45) 46 厳護(46)
46 厳護(46) 47 厳護(47)
47 厳護(47) 48 厳護(48)
48 厳護(48) 49 厳護(49)
49 厳護(49) 50 厳護(50)
50 厳護(50) 51 厳護(51)
51 厳護(51) 52 厳護(52)
52 厳護(52) 53 厳護(53)
53 厳護(53) 54 厳護(54)
54 厳護(54) 55 厳護(55)
55 厳護(55) 56 厳護(56)
56 厳護(56)